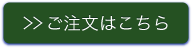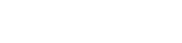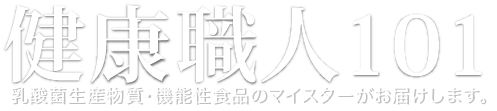
腸内環境学習かるた
解説ページ
● 初級編 ●
このサイトは、腸内カルタ(初級編)の読み札の内容を解説したものです。
日々、乳酸菌など腸内細菌に触れる仕事のなかで、初級編として主だった内容を挙げてみました。
腸内菌などの研究が進むにつれて、内容について誤っている部分が出てくる場合がありますが、
あくまで現時点に於ける当社の主観に基づいて記述した内容ですので、ご了承ください。
内容につきましては、順次修正を加える場合があります。
読み札解説
あ行
- あ青い鳥 あなたも持ってる 腸内菌
- メーテルリンク作の童話「青い鳥」をご存知でしょうか。病気の少女を救うため、幸せの青い鳥を探す旅に出たチルチルとミチルは、様々な世界を青い鳥を探して回りましたが、結局、探し当てる事ができずに家に戻ってきますが、なんと幸せの青い鳥は自分たちの家にいた、という童話です。 童話の意図は、幸福とは気がつかないだけでごく身の回りに潜んでいるもの、というストーリーです。現代人が健康という名の幸せを求めて彷徨う姿は、まるでチルチルとミチルのよう。自分の健康に本当に必要なものは、私たちが生まれた時から授かった免疫力という力。それを発揮する鍵はお腹の中にいる腸内細菌たちなのです。
- い胃酸には とっても弱いの 乳酸菌
- 乳酸菌に限らず、一般に微生物は酸や高温には弱いという特徴があります。胃壁かあら分泌される胃液には酸性度が高い塩酸が含まれており、胃の役目の一つとして、この酸によって食物に含まれていた病原菌などを殺菌して、十二指腸に送る、という仕組みになっています。 つまり、我々の栄養となる食物以外の生き物が入ってきた場合には、可能な限り殺して次に送る、というのが胃酸の目的ですので、病原菌に限らず乳酸菌などの微生物はすべて、酸で処理されることになります。「胃酸に強い乳酸菌」などというキャッチフレーズで売られている乳酸菌飲料などがありますが、これらは胃酸で乳酸菌が死なないように菌をカプセルでコーティングしたり、酸に強い遺伝子を持った乳酸菌を探して製品化するなどの処理をされたものです。 生きたまま胃を通過することを最大の特徴とした商品ですから、腸に届いた後でどのような仕事をしてくれるかは、はなはだ疑問です。
- う浮く沈む 腸のお便り バロメーター
- ウンチが浮くか沈むかは、ウンチの比重によって決まります。つまりウンチの中に気泡としてガスが多く含まれている場合は、水にプカッと浮くウンチになるのです。 一般にヒト腸内の場合は乳酸菌など善玉菌と呼ばれる菌が優勢となっている(数が多い)場合は、消化物発酵の時に菌がつくるガスがウンチに大量に含まれることになりますので、水に浮きやすいウンチとなります。 もちろん、このようなガスはウンチに含まれる他にも腸内に充満しオナラなどとして排出されることになります。もちろん、悪玉菌と呼ばれるような菌が優勢な場合には、ウンチに含まれるガスもウンチそのものも臭い臭いになります。
- えNKは 生まれながらの 殺し屋細胞
- ヒトの免疫システムは大きく分けて2種類があり、それぞれ自然免疫と獲得免疫と呼ばれています。以前免疫は産まれながら自然に備わっていることからその名がつけられ、体にとって不要なバクテリアや老廃物などを攻撃したり、食べてしまったりして退治します。自然免疫システムを構成する代表選手がNK細胞です。 NKはナチュラルキラーの省略で、自然免疫の殺し屋とも言われる頼もしい細胞なのです。
- え栄養が 無ければ育たぬ バクテリア
- 乳酸菌に限らず、バクテリア(菌)も生き物ですので、栄養源がなければ生きていけません。腸内細菌である乳酸菌の場合は、砂糖の一種である砂糖の一種であるグルコースが主な栄養源ですので、食物に含まれる糖分を栄養源として彼らは生きていることになります。 私たちが糖分として砂糖などを摂っていなくても、消化器官が分泌する酵素の働きで炭水化物が糖分に変換され、乳酸菌の栄養源となったりします。
- おお腹冷やすな 冷やすと増えない 腸内菌
- 昔から子供の頃には、「お腹を冷やすと風邪ひくぞ」などと言われていたものです。なぜお腹を冷やすと風邪をひくのかなど気にせずに、盲目的に親の言うことを聞いてきた方も多いと思います。結論から言いますと、お腹には腸内細菌が生息している腸があります。また体内をパトロールしているような免疫細胞の7割くらいが、腸のそばで腸内細菌と情報のやり取りをしていることが分かってきました。腸内細菌も免疫細胞も生き物ですので、彼らが最も快適に仕事ができる温度があります。これを至適(してき)温度と呼び、体温がその温度にあたります。 お腹が冷えると、彼らの環境温度が至適温度より低くなてしまうため、免疫力細胞の活性度の低下や免疫力の低下をもたらし、その結果免疫力が低下し、風邪をひきやすくなる、というわけです。昔の人はそんなメカニズムを知っていたわけはありませんので、先人の知恵、ということだと思います。
か行
- か加齢臭 ニオイの元は 代謝物
- オヤジ臭い加齢臭は中高年男性が嫌われる原因の一つですが、実は加齢臭の正体は皮膚に生息する常在菌の出す代謝物という成分のニオイなのです。皮膚常在菌は一生を通じて皮膚上に常に存在する様々な菌であり、常在菌が出す代謝物が、時にはバイキンを寄せけない働きをします。 しかし常在菌も年齢とともに種類が変わっていき、皮膚上の汗や老廃物を栄養源として生きている常在菌が出す代謝物も、質が変わっていきます。10代の若者には10代の常在菌が出す、若々しい代謝物の臭いがあり、中高年には中高年の常在菌が出す代謝物の臭いがあり、これが加齢臭と呼ばれる者の正体です。 このように私たちの体内外に生息している菌たちは、皮膚常在菌に限らず加齢の影響を受け、臭いだけでなく菌の受け持つ本来の働きも影響を受けます。
- き機能性 気のせい食品 ばかりかも
- 機能性を持つとして宣伝、販売されている食品はが数多くあります。特製機能性食品として、一部の機能性が認められている製品もありますが、通販やTV-CMなど大々的に宣伝されている製品の多くは、芸能人のキャラクターイメージで「膝に良い」「元気が出る」などの昨日を想像させる製品です。 もちろん、それらの機能性につながる成分が配合されてはいるのですが、食品に機能性を表示できないという法的な規制もあるとはいえ、効果に疑問符がつく製品が少なくありません。 それらの食品のことを私たちは機能性食品ではなく「気のせい食品」と読んでいます。飲んだり食べたりしても効果が期待できない、効果があってもそれは気のせい、という」レベルの製品です。
- くグルコース 菌の好物 甘いもの
- 乳酸菌など、腸内に生息する腸内細菌たちには、糖分を栄養源として生きています。しかし、糖分と言っても私たちの食卓に乗っている白砂糖(ショ糖:スクロースとも呼ぶ)だけでなく、糖がいくつか繋がって鎖状になっているオリゴ糖など、長さの違う糖が食品中には存在します。 腸内菌にはそれぞれ糖の種類に好みがあり、乳酸菌はスクロースよりもグルコース(ブドウ糖)や果糖(フルクトース)の方が好みです。特にグルコースは、そのまま私たちの身体中の脂肪のエネルギーとしても利用されるので、菌の好物だけでなく細胞の好物と読んでも良いでしょう。
- け嫌気性 腸内宇宙に 酸素なし
- バクテリア(菌)には嫌気(けんき)性と呼ばれる、酸素を嫌う細菌も多いのですが、私たちの腸内にいる乳酸菌は酸素があっても生きられる通性嫌気性と呼ばれる菌です。厳密な意味では腸内に全く酸素がないわけではありませんが、善玉菌の代表選手であるビフィズス菌は、偏性嫌気性菌と呼ばれ、通性嫌気性菌よりも酸素を嫌う性質があります。 できれば宇宙空間のような環境の方が、ビフィズス菌は元気に育つのです。
- こ献立で 菌の活性 変わります
- 腸内では、消化酵素によって消化物が分解され腸壁から吸収される一方、腸内細菌たちも消化物を栄養源として発酵が行われ、消化物が分解されていくという、二つの分解吸収作業が同時に行われます。 つまり、栄養分の奪い合いのようなことが起きているのですが、消化酵素では分解できない食物繊維やオリゴ糖などの長い構造の糖は腸内細菌のみが分解できます。
さ行
- さ酸素が なにより嫌いな ビフィズス菌
- 腸内細菌の中でも、善玉菌の代表選手であるビフィズス菌は偏性嫌気性菌と呼ばれ、とても酸素を嫌う性質があります。そこで、 ビフィズス菌を使ってヨーグルトや乳酸菌飲料を作る場合は、ビフィズス菌に、酸素を消費する性質を持つような乳酸菌を混ぜて発酵させ、乳酸菌がビフィズス菌の発酵を助ける形で製品を作ります。 またヨーグルトメーカーも、ビフィズス菌をなるべく酸素に触れさせないため、様々な工夫を行っています。 ビフィズス菌が入ったヨーグルトを食べる際には、むやみにかき混ぜて菌が空気に触れないようにした方が、ビフィズス菌の生存率は上がります。 しかし、その菌が胃酸で死滅せず、また腸内に届いた際にどのような働きができるかは、全く別の話です。
- し脂肪細胞 細胞だから 生きている
- 脂肪と聞くとバターやマーガリンのような油の塊を想像されると思います。しかし私たちの体内にある脂肪には、皮膚や筋肉の元になっている細胞と同じ棟に、細胞核があるのです。 脂肪に細胞核があるということは、脂肪が生きているということになります。スーパーで売られているバターは生きていませんので、当然いくら栄養素を与えても大きくなったり量が増えたりはしません。しかし、私たちの体内にある脂肪は生きていますので、栄養を与えればどんどん大きくなります。 ですので、過食や栄養過多の状態に成ると脂肪(細胞)が大きくなっていき、「太った」と言われるようになるのです。
- す好き嫌い 腸内菌にも あるみたい
- ヒトの腸内にはそれぞれ、数百種類、数百兆匹とも言われる大量の腸内細菌が存在します。それぞれ同じ種類の菌はコロニーと呼ばれる集落を作り、塊となって生息しています。菌の栄養源は基本的にはグルコースなどの糖分ですが、ビフィズス菌などの一部の菌は 食物繊維をも消化(資化といいます)します。それらの栄養源は私たちの食べた食物に含まれているわけですが、糖や食物繊維にも細かい種類や性質があるので、菌の種類によって消化しやすいもの、しにくいものが存在します。それらを菌の好き機いとは呼びませんが、菌によって好んで消化する成分があることは事実なのです。
- せ世界に一つだけ 腸内フローラ オンリーワン
- ヒトの腸内にはそれぞれ、数百種類、数百兆匹とも言われる腸内細菌が存在します。これらの腸内細菌はそれぞれ種類も数も人によって違うわけで、親子や兄弟でも全く違う種類の菌が優勢(数が多い)であったりします。 いわば人それぞれ、オンリーワンの腸内菌叢(そう)が存在しているのです。
- そそのサプリ 5W1Hを 確かめよう
- 市販のサプリメントは、メーカーでの安全基準に基づき、様々な検査をパスした安全な健康食品かと思います。サプリの形になってしまえば、サプリの原料がいつどこで誰に作られ、どのように加工されてきたかなど、いわゆる5W1Hがすべて分からなくなってしまします。 スーパーなどで売られている通常の食品であれば、比較的5W1Hにこだわる方も多いのですが、サプリの場合は原産国と消費期限が表示される程度です。サプリに限らず加工食品の場合は、農薬も添加物もキャリーオーバーとして表示はしなくても良いことになっています。 目的を持って口に入れる食品ですので、一般食品と同じように商品の5W1Hについての情報を、なるべくINETなどで取得しましょう。
た行
- た食べ物は 腸内菌の 餌となる
- 私たちが食物として食べた物は、唾液に始まる消化酵素により分解されながら次第に小さな物質成分に変化しながら腸に向かいます。消化物が腸内細菌に届く頃には、食品の中のタンパク質はアミノ酸の大きさにまで小さく分解され、炭水化物は消化酵素の働きで糖類に分解されています。 腸内細菌の餌となるのは最終的にはグルコース(ブドウ糖)ですので、そのためにたくさんの働きがあって腸内菌に栄養素としてにたどり着くことになります。
- ち腸内の 陣取り合戦 新参者は 追い出され
- 腸内細菌の種類や数、状態は様々な遍歴を経て現在のバランス状態に至っています。そのような腸内細菌の状態は、免疫機構に許容された自分の腸内細菌のみが棲みつくことができることや、経口免疫寛容と言って、口から食物として入って来た栄養源を排除せず、消化九州の対象物とするような、まるで意思をもったように自己、あるいは自己に必要なものと非自己を明確に分けています。 非自己である別の種類の菌が入ってきた場合には、たとえそれが病原性の菌でなく一般的な乳酸菌であったとしても、結局は便として排除されることになります。言うなればこのシステムは人の免疫力そのものとも言えます。
- つ翼より 私にください 免疫力
- 地球に最初の生命が誕生したのは約38億年前。人類の先祖である霊長類が出現したのは、今から約6500万年前。恐竜が絶滅する少し前と推測されているそうです。その頃から私たちの体を守っているのは遺伝子(DNA)に刻み込まれたプログラムに基づく免疫力です。 体内に侵入した異物を排除し、体内で発生したほとんどのトラブルを解決する素晴らしい力である免疫力は、当然老化とともに低下していきます。何才になっても高い免疫力が維持できていれば、臓器の寿命まで生きていることができ、それは125才だという説があります。
- て手も足も ない腸内菌が 命守る
- 腸内細菌と免疫系の働きは切り離さないほど密接な関係を持っています。体内の免疫系は病原菌やウイルスなどは徹底的に攻撃しますが、腸内細菌は攻撃せずに良好な友好関係が築かれています。 最近の研究では、腸内細菌の菌体成分や作り出す成分が、免疫系に対して働きかけ健康に大きく影響していることが判明しました。言い換えれば、手も足もない単細胞生物である腸内細菌たちが私たちの体を守っているとも言えます。
- と時には必要 飢餓状態
- 飢餓状態を勧めるものではありませんが、 飽食や過食の時代とも言われる現代。欧米化した食生活の中で知らず知らずのうちに過剰な栄養素を摂取しているのが現代人かもしれません。 私たちの消化器官のうち、腸内細菌がちゃんとしていれば、たとえ貧しい食材であっても、それを代謝し、栄養素に変えて宿主を助けてくれるようにできています。 人間がタンパク質を食べなければならないのは、タンパク質の構成要素であるアミノ酸を自前で作り出すだけの代謝能力・合成能力を持っていないからである。20種類あるアミノ酸の中には、自分の体内で作れるアミノ酸もあるが、必須アミノ酸は作ることができない。だからこれは食品として摂取するしかない。 腸内細菌のような微生物は、単純な資材(たとえば炭水化物といった糖質と窒素源であるアンモニア)からすべてのアミノ酸を全部自前で作り出す万能の合成能力をもっている。炭水化物は炭素と水素と酸素からできているので、窒素を含むアミノ酸を作り出すには必ず窒素源となる物質が必要となる。人間は、たとえこれら資材がそろっていたとしても、化学反応を起こすための酵素を持っていないので、必須アミノ酸を作り出せないのである。 人間は、栄養価の高い食物を確保することによって、必須アミノ酸を安定して得ることに成功したが、一方で、微生物との共生関係を維持することによっても生存率を高めた。それが腸内細菌だ。
な行
- な何よりも 菌が大好き グルコース
- 糖類にも様々な種類がありますが、乳酸菌が栄養として受け入れるのはグルコース(ブドウ糖)です。
- に人間の 細胞より多い 腸内菌 お金に変えれば 大金持ち
- ヒト腸内には数百兆匹とも云われる腸内細菌が生息しています。私たちの体を構成している細胞の数は約60兆個と云われていますので、その数より多いことになります。 もし腸内細菌1匹を1円と感情すれば、腸内細菌は数百兆円に匹敵する数ということになります。 ちなみにそれらの腸内細菌の重さは約1Kgですので、同じ発音の金の価格が1gで5.000円(2017年12月)と同等だすると500万円相当の重さになります。
- に乳酸を 生産するから 乳酸菌
- 細菌学者として有名なパスツールは、糖から乳酸菌が乳酸を作り出すことを発見しました。これを乳酸発酵と呼びますが、乳酸発酵には大きく分けて2種類があります。 ヒトの腸内にいる乳酸菌のように単に乳酸を生成する乳酸だけを生成するホモ乳酸発酵と、乳酸の生成と同時に他の種々の生成物(エタノール、酢酸、炭酸ガスなど)を生成するヘテロ乳酸発酵があります。 醸造メーカーなどはヘテロ乳酸発酵を行う乳酸菌を選んで製品を作り出します。
- ぬぬるま湯は 腸内菌の 好きな温度
- 腸内細菌に限らず、菌類にはそれぞれ生きていくために最適な温度があり、それを至適(してき)温度と呼びます。食品を冷蔵庫で長い時間保存することができるのは、食品中の雑菌やバイキンなどは常温ではどんどん増殖して食品を腐らせるなどの害を与えますが、4 ℃ほどまで温度を下げ冷やすことで、至適温度から温度を下げ、菌の活動ができないようにするからです。腸内細菌が好きな温度は私たちの体温と同じ温度。ちょうどぬるま湯の温度くらいとも言えます。
- ねネバネバが 腸内細菌 好きなのよ
- 水溶性食物繊維とは水に溶ける性質を持った食物繊維です。フコイダンやペクチン、ムチンなどいろいろな種類がありゲル状になったりネバネバしたものが多いのが特徴です。 便秘の時に摂取した方がいいのはこの水溶性食物繊維です。ゲル状・ネバネバといった性質から便が腸の中をツルリと移動しやすく、保水性も高いため便の水分量を増やしやわらかくするため便通の改善に役立ってくれます。 水溶性食物繊維は不溶性食物繊維に比べ腸内細菌に分解されやすく、腸内の善玉菌を増やす効果も期待できます。水溶性食物繊維が多い食材順に表示すると、 らっきょう エシャロット にんにく ごぼう えだまめ オクラと続きます。今までのネバネバのイメージと、かなり違いませんか?
- ね寝てる間の ターンオーバー 大切に
- 皮膚が入れ替わることをターンオーバーとも呼びますが、私たちの表皮がターンーバーする時間帯は、夜の10時頃から夜中の2時頃がゴールデンタイムと言われてきました。夜更かしをしてこの時間帯に睡眠していないと、 傷ついた細胞や入れ替えが必要な細胞の入れ替えが行われにくくなります。 それはそのまま老化を加速する結果にもなるわけです。しかし最近では、成長ホルモンが分泌されやすいのは入眠後の3〜4時間であって、特定の時間帯には限定されていないという説が有力になってきています。いずれにしても、夜は早めにしっかりと睡眠をとるということが、老化を遅くし美容にも効果的であることに変わりはありません。
- の脳腸相関 第二の脳と 腸を呼ぶ
- 腸内と脳が相関している、つまり繋がっていてお互いに何らかの影響があるということが、最近の研究でわかってきました。TV番組でも特集が組まれたりしていますが、実際に腸のどの部分と、脳のどの部分が影響しあっているのかなど、詳しいことはまだわかっていません。 ただ漠然と、腸の調子が悪いとイライラするのは脳とつながっているからだとか、不安があると下痢をする(自律神経系の反応と言われています)など、感じることは多いと思いますが、脳と腸が関係しているという仕組みも次第に明らかになってきたのです。
は行
- は発酵と 腐敗の違い 紙一重
- 菌が栄養分を得て増殖し、代謝物を放出するという作業は、発酵であれ腐敗であれ同じ作業です。私たちがそれを発酵と呼んだり腐敗と呼ぶのは、主体となる菌や培地(栄養源)をコントロールしているか否か、あるいは私たちに有害な物質が代謝されているかどうか、などの違いのみです。
- ひ百種以上 数百億の 腸内菌
- ヒト腸内には数百兆匹とも云われる腸内細菌が生息しています。私たちの体を構成している細胞の数は約60兆個と云われていますので、その数より多いことになります。
- ふフローラだけ 良くても病気は 治らない
- 腸内細菌の研究が進み、腸内フローラの状態が私たちの健康に大きく影響を与えていることは、今や常識とさえ言われるようになってきました。しかし、腸内細菌のバランスが安定しているとしても、加齢に伴い菌自体の活性度は低下していくため、免疫機構の一部としての腸内菌の働きも低下していきます。お通じや消化吸収機能とは別に、良好な免疫力を維持できているかという面で、腸内フローラを捉えるべきだと言えます。
- へ便秘なの 下剤でフローラ 悪循環
- 女性にとって便秘は大きな悩みの一つだと思います。確かに、毎日排便が出来ないことで、精神的にイライラするだけでなく、人それぞれ多種多様なトラブルを生じることも事実です。 しかし、毎日の排便を習慣化しようとするあまり、下剤で無理やり腸を動かし排便を促すことが、腸内フローラの状態をも悪化させ、さらなる悪循環を引き起こす結果になる場合も少なくありません。 何日もお通じがなく苦しい状態を回避するために、止むを得ず下剤を処方する場合もあると思いますが、これらの薬剤が必ずしも腸内フローラの状態を改善するとは限らないことを認識すべきです。 食物繊維などによって排便を促すなどの方法は積極的な方法ではありませんが、本来あるべき状態に戻すために何かできるのか、目的を排便ではなく腸内フローラの改善という観点でお考えいただきたいと思います。
- ほホルモンは 微量で健康 左右する
- 私たちの体内は、いつも一定の状態に保たれていて、これをホメオスターシス(恒常性)といいます。この恒常性が維持できなくなると健康が損なわれ、生命にまで危険になります。 このホメオスターシスを維持するシステムは二つあり、一つが神経系で、もう一つがホルモンです。 体内にはホルモンを作る器官がたくさんあり、体内の状態が通常状態から外れるとホルモンをつくる細胞(内分泌腺と言います)からホルモンが分泌され、神経系と共に体内を元の状態に戻そうとします。 ホルモンは、非常に微量でその作用を発揮し、血液などの体液中での濃度が極めて微量でも機能を発揮します。女性ホルモンのエストロゲンなどは有名ですが、ホルモンはもともと「呼び覚ます」という意味のギリシア語で、眠っている状態から目覚めさせ、成長や代謝を促す作用があるところからこの名称がつけられました。
ま行
- ま毎日の お便りばかりを 心配し フローラ乱して 悪循環
- 女性にとって便秘は大きな悩みの一つだと思います。確かに、毎日排便が出来ないことで、精神的にイライラするだけでなく、人それぞれ多種多様なトラブルを生じることも事実です。 しかし、毎日の排便を習慣化しようとするあまり、下剤で無理やり腸を動かし排便を促すことが、腸内フローラの状態をも悪化させ、さらなる悪循環を引き起こす結果になる場合も少なくありません。 何日もお通じがなく苦しい状態を回避するために、止むを得ず下剤を処方する場合もあると思いますが、これらの薬剤が必ずしも腸内フローラの状態を改善するとは限らないことを認識すべきです。 食物繊維などによって排便を促すなどの方法は積極的な方法ではありませんが、本来あるべき状態に戻すために何かできるのか、目的を排便ではなく腸内フローラの改善という観点でお考えいただきたいと思います。
- みミリよりも 千分の一小さい 腸内菌
- ミクロンは長さの単位で、1ミリメートルの1000分の1。現在は1μmマイクロメートルという単位です。乳酸菌の大きさはおおよそ0.5~10μm(マイクロメートル)ぐらいの大きさですので、やはり1ミリの1000分の1から100分 の1の大きさということになります。何れにしても目で見てわかる大きさではありませんので、顕微鏡レベルの大きさ、ということになります。
- む無理しても 善玉増えない 金の無駄
- 腸内フローラを構成する細菌の状態は、このように何十年といった長い時間をかけて変化していくものですので、一時的に下痢をしたり便秘になった事で、腸内フローラが簡単に入れ替わってしまう事はありません。 腸内の状態というものはやじろべえの様に、一定の細菌の種類や数が安定して保たれる仕組みになっています。これを恒常性と言います。恒常性のおかげで、たとえヨーグルトや乳酸菌飲料など善玉菌を飲んで腸に送り込んだとしても、腸はすぐさまそれらを異物として排泄してしまい、元の状態に戻ります。
- め免疫は 自己と非自己を 見分ける力
- 免疫という言葉は、病気や外敵(疫)から免(まぬが)れるための仕組みからきています。私たちの体は免疫機能に守られていますので、なかなか病気にはかからず、80年以上も生きることができるのです。 大まかに言いますと、実際の免疫機能は常に自分のからだと同じものを自己、異なるものを非自己として認識していて、区別して扱っています。 そしてもし、非自己が体内に侵入してきた場合にのみ、これに反応して排除しようとします。この場合の非自己を抗原(こうげん)といいます。そして、抗原の侵入に対するこのようなからだの反応を免疫応答といいます。 万が一、自己であるものを非自己と誤って認め、それを排除しようとする免疫応答がおこると、自己免疫疾患がおこります。リューマチなどは自己を非自己として認識してしまい、攻撃するために痛みが生じてしまう、自己免疫疾患と言われています。
- ももしかして フローラ相性 良いのかも
脳腸相関
腸と脳の機能の一部が連携しているという、脳腸相関という考え方があります。相関という言葉には、腸の状態が脳に影響を与えるという方向と、脳の状態が腸に影響を与えるという双方向の働きがあります。 昔から、「腹黒い奴、腹の底から、腹を据えて・・・」など、腹という部分がヒトの精神部分に関与しているという考え方が根強く残っているのも、脳腸相関が現実的な現象として私たちの中に浸透してきたのだと思われます。 そう考えますと、私たちが頭の中で感じたり考えたりしている様々な事に、腸内フローラが関与していることを、現実的に考えざるをえません。脳のコミュニケーション
日夜、腸内細菌を扱っている私たちの感覚では、腸内細菌は直接、試験管などの容器の中で混合され交わっていない場合でも、多少の距離を隔てた状態で影響を与え合っていることが確認されています。 現在はまだ飛躍した考え方かもしれませんが、人と人の相性が、相互の腸内細菌同士のコミュニケーション結果の影響を受けている可能性があります。もしかして・・・人と人の相性のような関係も、腸内フローラの種類によって変わるのかもしれません。
や行
- ややすやすと 腸内フローラ 変わりません
-
年齢と腸内フローラ
腸内フローラの年齢変化でまず思い浮かべるのは、東大名誉教授の光岡先生の描いたグラフです。 腸内細菌の数が年齢とともに変化し、若い頃には優勢(数が多い)だった善玉菌が年齢とともに減少し、替わって悪玉菌が増加していくさまがグラフに表されています。 腸内フローラを構成する細菌の状態は、このように何十年といった長い時間をかけて変化していくものですので、一時的に下痢をしたり便秘になった事で、腸内フローラが簡単に入れ替わってしまう事はありません。恒常性というはたらき
腸内の状態というものはやじろべえの様に、一定の細菌の種類や数が安定して保たれる仕組みになっています。これを恒常性と言います。恒常性のおかげで、たとえヨーグルトや乳酸菌飲料など善玉菌を飲んで腸に送り込んだとしても、腸はすぐさまそれらを異物として排泄してしまい、元の状態に戻ります。 つまり、様々な要因によって状態が悪化した腸内へ乳酸菌などを送り込み、直接腸内フローラを善玉菌優勢に変えてしまおうという乱暴な方法は、上記理由でさほど効果は期待できません。腸内フローラが悪化したら
そのような対処療法の前にまず行わなくてはならないことは、腸内フローラの悪化によって起きているトラブルの解消、最も重要なのは生命維持に直接関わっている、免疫力の低下などを改善することだと考えます。 実際に腸内に善玉菌が送り込まれたときには、腸内フローラが入れ替わることよりも、その善玉菌の菌体成分によって腸の免疫機構を刺激し、免疫力を回復させる事は期待できます。しかし、実際に免疫機構を刺激している割合としては、菌体そのものよりも菌が放出している液体成分の方が多いと考えられています。 - ゆ優秀な 菌と呼ばれる 乳酸菌 環境変われば ただのよそ者
- 乳酸菌メーカーが販売する乳酸菌について、その機能性をアピールする場合、その方法はだいたい決まっており、多くは乳酸菌単体での免疫活性を調べたり、悪玉ホルモンを低減させる機能などが測定されます。 乳酸菌を使ったこれらの試験の多くは、1種類の乳酸菌単体で行われるため、実際にそのような乳酸菌を私たちが製品として飲んだ場合、私たちの腸の中で同じことが起こるかどうかは、また別の話です。 腸内にたどり着いた際に、非自己、つまりもともと自分の腸内にいる乳酸菌でない場合は、圧倒的に多くの既存の腸内細菌に攻撃される(排除される)運命にあります。
- よよそ者を 全て追い出す 腸内菌
- 腸内フローラを構成する細菌の状態は、 出生直後から何十年といった長い時間をかけて変化していくなかで現在の腸内フローラに落ち着いていると言えます。腸内細菌は、自分たちの仲間とそうでない他の菌とを明確に区別することができますので、乳酸菌であれ病原菌であれ、腸内に届いた菌は全て追い出されます。 腸内へ乳酸菌飲料などで乳酸菌を送り込み、直接腸内フローラを別の菌を優勢に変えてしまおうという乱暴な方法は、効果は期待できません。
- よヨーグルト 健康願って ワンコイン
- 健康のため、と100円前後のヨーグルトに様々な願いを込めて飲んでいる方も多いと思います。
食品としてのヨーグルトや、ある程度の機能性が証明されている乳酸菌を使用した乳酸菌飲料などが健康に良いとされることを、あえて否定するつもりはありません。 が、乳酸菌を飲んでいれば健康になるとか、ヨーグルトを食べていれば免疫力が上がるなど、過度の期待をすることには否定的です。1g中に○○匹の乳酸菌が含まれている、などグラムあたりの乳酸菌の数を強調している商品も見受けられますが、乳酸菌の機能性は数で決まるものではなく、非自己の菌としてすぐに排泄されることを前提とした宣伝とも言えます。
ら行
- らライバルが いるから頑張る 腸内細菌
- 腸内フローラを構成する細菌の状態は、 出生直後から何十年といった長い時間をかけて変化していくなかで現在の腸内フローラに落ち着いていると言えます。 腸内細菌は、自分たちの仲間とそうでない他の菌とを明確に区別することができますので、乳酸菌であれ病原菌であれ、腸内に届いた菌は全て追い出されます。
- り臨床で 最終確認 機能性
- 薬であれ機能性成分であれ、その薬効や機能性を確認し商品として販売するには、様々なステップを踏んで確認することが求められ、これをASSY(アッセイ)と呼びます。 最近では、生きた動物を使ったバイオアッセイは動物保護の観点からもなかなか実施しにくくなってきました。バイオアッセイに変わって増えているのが生きた細胞を使ったセルアッセイです。 セルアッセイなどで特定成分の機能性が確認された後は、いよいよ最終的にヒト臨床試験によるアッセイが行われます。 しかし動物や脂肪と違って、人間の場合には安全性の補償はもちろんですが、意識を持った人間ですので結果を左右する多くの問題があります。その一つがプラシーボ効果と言われるもので、「この薬は糖尿病に効果があるのですよ」などと先入観年を与えられてしまいますと、実際は効果がない薬でも血糖値が下がるなどの結果が出てしまう場合があるのです。 このようなことが起こらないように、臨床試験は臨床薬理学という学問によって科学的に確立された方法に従って行われる必要があるのです。 ところが、このような科学的に確立された方法をとらずに行われる臨床試験が多いのも事実で、残念ながら、そのような試験結果の信ぴょう性には疑問が出てきます。
- るルビーより ダイヤより貴重な 免疫力
- ヒト腸内には数百兆匹とも云われる腸内細菌が生息しています。その腸内細菌は腸管免疫機構を介して私たちの免疫に大きく関与していることが分かってきました。 免疫という言葉は文字通り、病気や外敵(疫)から免(まぬが)れるための仕組みですので、私たちの体は免疫機能に守られているおかげでなかなか病気にはかからず、80年以上も生きることができるのです。 免疫機構の価値をお金に換算することなどできませんが、その存在は私たちにとってまさしく宝石のように貴重な存在であると言えるでしょう。
- るルックスより フローラ気になる 未来のお見合い
- ヒトの寿命は細胞内の遺伝子に刻み込まれた内容によって決まっていますが、それはいわば臓器の寿命とも言えます、実際はどのような食生活を送るか、肉体的、精神的なストレスの加わり方などによっても、大きく影響があることもあります。 しかし一方で、腸内フローラと呼ばれる腸内菌の集まりによって、腸内細菌の影響は 免疫力の強さなど健康面だけでなく、宿主(しゅくしゅ)である私たちの性格などにも影響を与えている可能性があります。 現時点で、どのような腸内フローラを持っているのかを調べる技術が進んでいますので、健康情報の一つとして腸内フローラの状態がラインナップされる可能性もあるのではないでしょうか。近い将来、お見合い写真と一緒にお相手の腸内フローラをきにする時代が来るかも・・・
- れ冷凍は急速 解凍は 緩慢が基本
- 表題は間違いで、正しくは「冷凍は緩慢 解凍は 急速が基本」です。
一般家庭で使われている冷凍庫は、緩慢冷凍と呼ばれる技術での冷凍になります。水分が少ない食品に関しては緩慢冷凍でも問題ありませんが、水分を多く含んでいる食品や、私たちが実験用に冷凍する細胞などの場合、 凍結される際に水分が大きな氷の 結晶ができてしまい、細胞壁が破られるドリップという現象を起こしてしまいます。 このため冷凍はゆっくり温度を下げてマイルドな氷の結晶を作り、かつ膨張しない氷を作ることが大事です。
逆に、解凍する際はその逆で一気に温度を上げて溶かす必要があります。ゆっくり解凍して温度が0度付近になると、少しの刺激でも再凍結してしまうことがあるからです。 一般の食品を解凍するなら冷蔵庫による低温解凍が一般的です。冷蔵庫内は低温で安定しているので、時間はかかりますが品質を守りながら解凍することができます。 加熱調理してある食品や、解凍から加熱まで行いたい食品の場合には電子レンジでの急速解凍が適しています。 結局、生きている細胞や鮮度が重要な食品などの場合は、ゆっくり凍結・急速解凍が基本になります。 - ろ老衰で 最後を迎える 幸せさ
- 日常生活に制限のない期間(健康寿命)は、平成25(2013)年時点で男性が71.19年、女性が74.21年となっており、それぞれ13(2001)年と比べて延びています。 しかし、13(2001)年から25(2013)年までの健康寿命の延び(男性1.79年、女性1.56年)は、同期間における平均寿命の延び(男性2.14年、女性1.68年)と比べて小さいのは、生きているが健康ではない、あるいは寝たきりになっている人が増加しているということを示しています。 若い時のように完全な健康体ではないにせよ、延命技術のはったつにより、人間らしく生き、最後は老衰によって最期を迎えられることが難しい時代だとも言えます。
わ行
- わ悪者が いないとドラマは 成り立たぬ
- 善玉菌・悪玉菌と言われ分けられている腸内細菌ですが、実は数の上では善玉でも悪玉でもない日和見菌と呼ばれる菌の数が一番多いと言われています。日和見菌は、腸内の状況によっては、人に良くも悪くも働くため、このように言われています。では、腸内細菌が全てビフィズス菌などの善玉菌であれば良いのか、悪玉菌は 全くいない方が良いのかと言えば、そのようなことはありません。善玉菌も悪玉菌も日和見菌も、その人なりのバランスをもって共存していることが重要で、どちらかの菌が多い方が良い、ということはありません。
その他
- び微絨毛 広げて畳が 242枚分
- 腸は1本のパイプのような構造ですが、腸壁を拡大してみると絨毛(じゅうもう)と呼ばれる絨毯の毛のようなものがぎっしりと生えています。 さらに絨毛の表面を拡大すると微絨毛(びじゅうもう)と呼ばれる細い毛のような繊維状に枝分かれしたものが存在しており、全体として腸壁の面積を増やしていることになります。 これら、絨毛や微絨毛の表面積を全て合わせると約400m2とも言われ、これは畳242枚に相当する広い面積ということになります。 腸内ではこの畳242枚の面積にびっしりと腸内細菌が棲(す)みついていて、私たちの食べた食品が消化物となったものを栄養源に、様々な活動をしているのです。